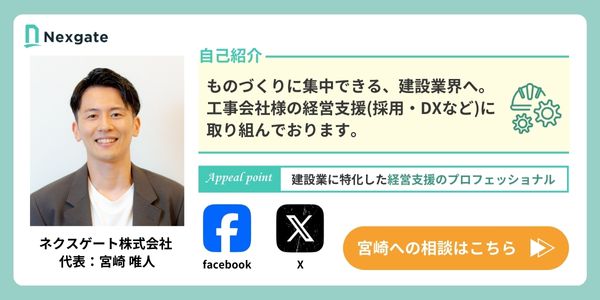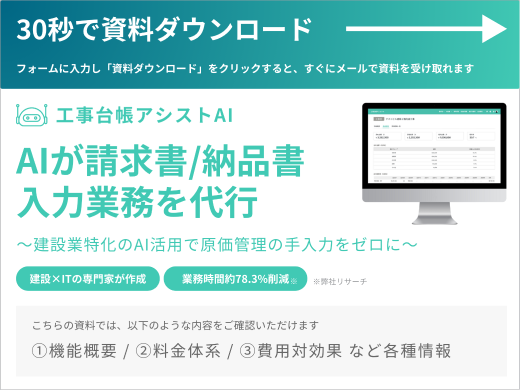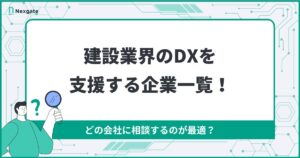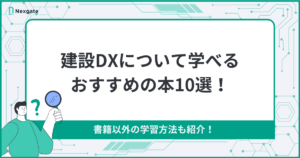建設DXに費用はいくらかかる?コストを抑えて進める方法を解説!
建設DXに向けたデジタルツールを導入するにあたって、最も気になるのが「費用」です。
初期費用だけでなく、従業員全員がツールを使えるようにするための設備投資や、継続的に活用するためのランニングコストなども見越しておく必要があります。

「今流行っているから…」と軽率に取り入れると、先々で資金繰りが苦しくなり、自社の首を締めることにもなりかねません。
そこで今回の記事では、建設DXの導入に際して必要な費用の目安をジャンル別・ツール別にご紹介していきます!
▼建設DXについてお悩みの方はお気軽にご相談ください!

業界の人手不足や働き方改革が強く求められる昨今
建設業界でのデジタル化や生産プロセスの効率化や自動化は必須!

建設業に精通した私たちだからこそできる、経営支援を提供します!
\建設DXのプロが30分で解決/

建設DX導入にかかる費用の内訳
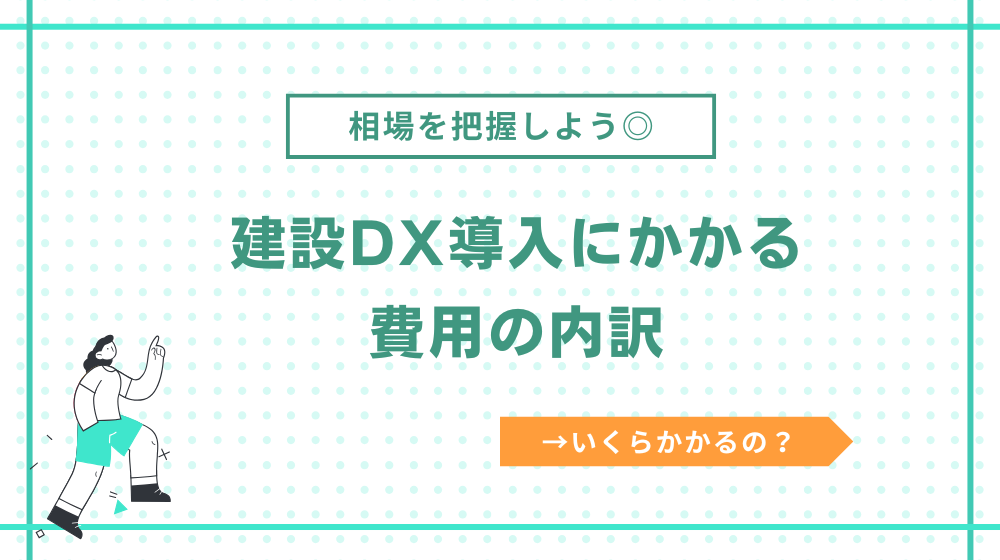
建設DXによって「業務の効率化ができた」「ミスが減った」といった成功事例がある一方で、同じくらい「とにかくお金がかかる」という声も耳にします。
実際のところ、DX導入にかかる費用はシステムの規模や機能、トータルの使用期間などによって大きく異なります。

まずは、建設DX導入にかかる主な費用項目を4つに分けて整理し、それぞれのおおよその金額感を知っておきましょう。
| 費用項目 | 概要 | 想定費用(目安) |
|---|---|---|
| 初期費用(導入・構築) | システム購入費 アカウント発行 初期設定など | 約10万円〜200万円 |
| 月額/運用コスト | サブスクリプション利用料 保守サポート費用など | 月額5,000円〜10万円 |
| 社内研修・教育コスト | 従業員向けの操作研修 業務マニュアル作成費など | 0円〜20万円 |
| カスタマイズ費用・外注費 | 自社専用の仕様変更や 導入サポートの外部委託など | 約10万円〜100万円 |
あくまでも目安ではありますが、費用の全体像をつかむことで、無理のない計画づくりにつながります。
初期費用(導入・システム構築)→約10万円〜200万円
システムの規模が小さければ10万円程度からスタートできますが、大規模なシステム連携や複数拠点での利用を想定する場合は、200万円近くかかることもあります。
具体的な初期費用の内訳としては、以下のような設備費用が大半を占めています。
- クラウド型ツールのライセンス料
- サーバーの契約料
- アカウントの開設費
- その他初期設定や環境構築の費用

ほとんどの場合、最初がいちばんコストがかかります。
ここでコストを惜しむと後々修繕費やアップデート費用が発生することになるので、なるべくケチらないことが肝心です。
月額/運用コスト(サブスク・保守費用)→月5,000円〜10万円
DXツールの多くはサブスクリプション型の課金体系ですので、月額費用として利用料が発生します。
費用は導入する機能やユーザー数によって異なり、簡易的な現場管理アプリであれば5,000円前後から利用可能です。
一方、図面管理・工程管理・帳票出力などの多機能プランを利用する場合や、サポート体制が充実したサービスを選ぶと月額10万円以上になることもあります。
社内研修・教育コスト→0円〜20万円
こちらは必須ではありませんが、中小以上の規模で新しいシステムを導入する際には、従業員への操作研修や社内マニュアルの整備をしておくのがベターです。
Excelやパワポで簡易的にまとめられるケースもあれば、外部講師を招いた研修の場を設けることで数万円〜20万円程度かかる場合もあります。

ITに不慣れなスタッフが多い現場や従業員の平均年齢が高い現場では、初期段階でしっかりと研修を行っておくことで、導入後の定着率が大きく変わります。
カスタマイズ費用や外注費→約10万円〜100万円
自社の業務フローに合わせてツールをカスタマイズしたい場合や、導入作業を外部業者に依頼する場合には追加費用が発生します。

規模によって費用は異なりますが、おおむね10万円〜100万円が目安となります。
たとえば、「自社独自の帳票フォーマットに対応させたい」「特定の他システムと連携させたい」といった要望がある場合、それに応じた仕様変更や開発が必要です。
建設DXツール別の費用相場まとめ
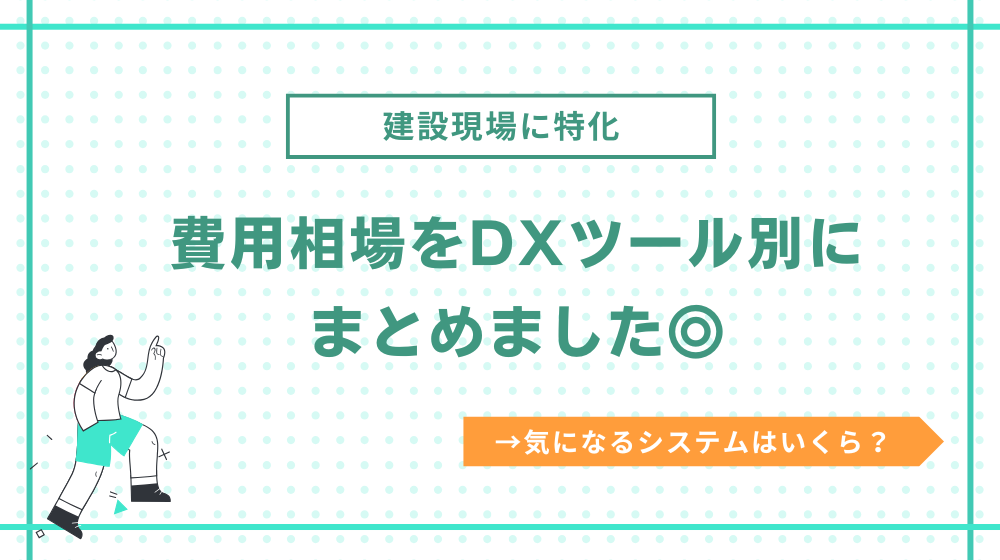
導入コストはDXツールの種類や提供企業、契約プランによって異なりますが、おおよそでも構わないので相場を把握しておくことは必要です。
本章では、建設業でよく利用されている代表的なDXツールについて、機能別に費用の目安を見ていきましょう。
原価・工程管理システムの費用相場
収益性に直結する原価・工程管理システムは、建設DXの中でも特に導入例が多いツールです。
現場と事務所の情報をリアルタイムで連携できるクラウド型のものが多く、ユーザー数あたりで換算されるプランが大半を占めています。
原価・工程管理システムの導入費用の目安
・初期費用:10万〜50万円程度(アカウント発行・初期設定・導入サポートなど)
・月額費用:1万〜5万円(1ユーザーあたり)
・代表的なサービス:「ANDPAD原価管理」「ダンドリワーク」「Aippear」など
中小企業向けの簡易プランであれば、月額1万円台から導入可能なケースもあります。
▶こちらもチェック:建設業向けの原価管理ソフト10選!自社に最適なシステムを選ぶポイントも解説!
勤怠管理アプリの費用相場
建設業では現場ごとに就業時間が異なることが多く、従来のタイムカードや手書き日報では管理が煩雑になりがちです。
そのため、最近では手元のスマホで打刻ができる勤怠アプリの導入が進んでいます。
勤怠管理アプリの導入費用の目安
・初期費用:無料〜3万円(システム登録、初期設定サポートなど)
・月額費用:300円〜600円/人
・代表的なサービス:「KING OF TIME」「スマレジ・タイムカード」「ジョブカン勤怠管理」など
▶こちらもチェック:建設業に対応した無料の出勤簿アプリを調査!完全無料〜コスパ最高の安価なサービスまで紹介。
中小規模の企業では、1人あたり月数百円で利用できるリーズナブルなプランが中心です。

すでに社用スマホが行き渡っている現場なら、アプリをインストールするだけで導入できることもあります。
そのほか、顔認証打刻や勤怠データの自動集計など、プラスαの機能を追加したい場合はオプションとして費用が発生します。
電子請求書・帳票ツールの費用相場
電子請求書・帳票ツールでは、帳票の発行件数が多い企業に対して割引価格が適用されるなど、建設DXのツールの中でもプランの価格帯が幅広いのが特徴です。
電子請求書・帳票ツールの導入費用の目安
・初期費用:0円〜10万円(アカウント発行・ソフトのインストールなど)
・月額費用:3,000円〜3万円(発行枚数・送信先件数・機能数によって変動)
・代表的なサービス:「工事台帳アシストAI」「BtoBプラットフォーム 請求書」「マネーフォワードクラウド請求書」など
インボイス対応機能や電子署名、PDF自動化など、利便性の高い機能を使うためには追加費用を払わないといけないケースもあります。
ペーパーレス化の流れを受けて、請求書・見積書・発注書などの帳票を電子化する動きは年々加速しています。
▶参考:建築業の請求書はどうやって電子化するべき?おすすめのシステムや注意点を解説!

弊社が開発・運用を手がけている「工事台帳アシストAI」なら、各企業様の規模感や業務フローに合った機能をご利用いただけます!
費用についてもご相談を承っていますので、まずは無料相談会にてお気軽にご相談ください。
写真共有・報告書アプリの費用相場
工事の進捗管理や現場報告を効率化するため、スマートフォンで撮影した写真をクラウドで共有・管理できるアプリも人気です。
写真共有・報告書アプリの導入費用の目安
・初期費用:0円〜10万円(利用ID登録、クラウド設定費用など)
・月額費用:5,000円〜3万円
・代表的なサービス:「蔵衛門(くらえもん)」「FieldPlus」「フォトラクション」など
工程ごとに写真を分類し、報告書として自動生成できる機能を活用すれば、現場からの直行直帰もできるようになります。
日常的に使うことになるので他のDXツールと比較して費用が少なく、手軽に導入できるのが魅力です。

ただし、複数現場での並行運用や容量無制限プランを選ぶとなると、月額費用はやや高めになります。
建設DXにかかる費用を抑える方法はある?
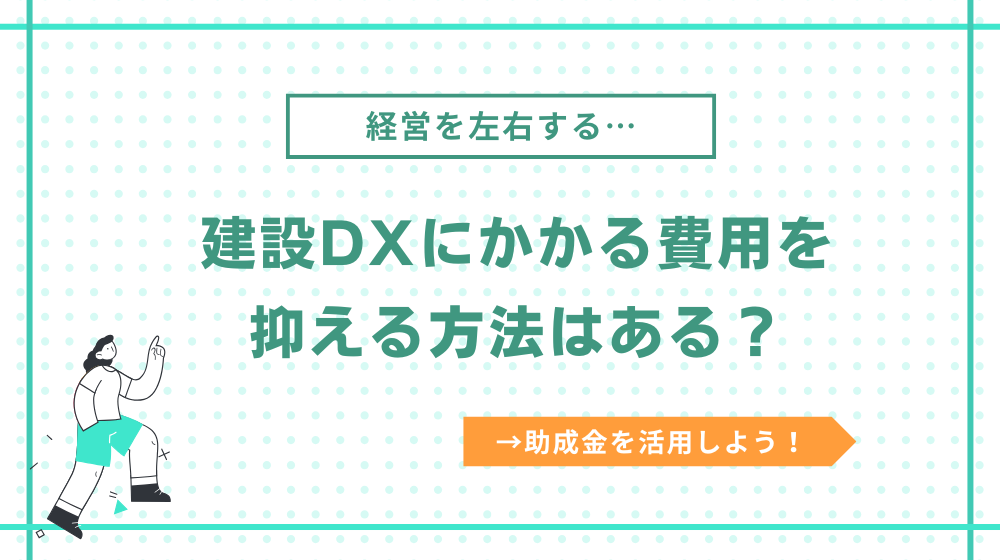
建設DXを進めるうえで、一定の初期投資や運用コストがかかるのは事実です。
しかし、工夫次第ではコストを抑えつつ、効果的にデジタル化を進めることも十分に可能です。
ここでは、費用を抑える3つの方法をご紹介します。
- 1.補助金を活用する→約50万円〜350万円の削減が期待
- 2.社内人材のみで進める→約10万円〜50万円の削減が期待
- 3.段階的に導入(スモールスタート)する →初期費用を最大80%カットできることも
1.補助金を活用する→約50万円〜350万円の削減が期待
最も効果的なコスト削減策の一つが、国や自治体が提供する補助金制度を活用することです。
代表的な制度には「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」、「小規模事業者持続化補助金」などがあります。

たとえばIT導入補助金では、クラウド型原価管理システムや勤怠管理アプリなどの導入費用が最大3分の2まで補助されることもあります。
| 補助金・助成金制度 | IT導入補助金 | ものづくり補助金 | 小規模事業者 持続化補助金 | 人材確保等 支援助成金 |
| 対象者 | 中小企業 (飲食、宿泊、卸・小売、運輸 医療、介護、保育等のサービス業のほか 製造業や建設業等も対象) | 中小企業者 組合 小規模事業者 特定非営利活動法人 社会福祉法人 など | 【対象経費】 機械装置等費 広報費、ウェブサイト関連費 展示会等出展費 など | 建設キャリアアップシステム (CCUS)を活用した雇用管理改善の取組を 行った中小建設事業主 など |
| 受給難易度 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 支給額 | 【通常枠】の場合 1プロセス以上:5万円以上150万円未満 4プロセス以上:150万円以上450万円以下 | 【製品・サービス高付加価値化枠】の場合 従業員5人以下:750万円 6~20人:1,000万円 21~50人: 1,500万円 | 補助率:2/3 (賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) | 【建設キャリアアップシステム等活用促進コース】の場合 算定対象となる建設技能者1人あたり16万円 |
| 公式サイト | https://it-shien.smrj.go.jp/ | https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html | https://r3.jizokukahojokin.info/ | 労働・雇用>人材確保等支援助成金のご案内 |
どの制度にも条件や申請手続きがありますが、正式な手順を踏んで準備すれば採択される可能性は高くなり、DX化にかかるコストを大幅カットできますよ。
2.社内人材のみで進める→約10万円〜50万円の削減が期待
外部コンサルタントやベンダーに、DX化の動き出しからシステムの選定、導入、運用まですべてを委託すると、導入支援費がかさみがちです。
プロにまとめて一任するのではなく、可能な範囲に限っては社内人材で対応するという方法もあります。
たとえば、無料の研修動画やマニュアルを活用して担当者自身が操作を学んだり、既存の業務フローに沿った簡易な使い方から始めたりすることで、初期の教育・外注コストを10万〜50万円と大幅に削減できます。
社内人材だけでDXを進める方法
①建設DXについて学べる本を読んでみる
建設DXとは何かをイチから学びたい人におすすめ。社内で知識をインプットするのにも◎
▶詳細:建設DXについて学べるおすすめ本10選!書籍以外の学習方法も紹介しています!
②建設DXに強いコンサル企業の無料相談を活用する
独学ではDXについて理解しきれない部分も多いため、建設DXに強いコンサルに質問してみる。ほとんどの企業では初回の相談は無料!
▶詳細:建設業界のDX進まない理由とは?最初にやるべきことも解説。

「設定や運用の一部は自分たちでやる」という意識を持つことで、一人ひとりの建設DXへの意識も変わってくるので、とくに従業員数の少ない中小建設会社では有効です。
3.段階的に導入(スモールスタート)する →初期費用を最大80%カットできることも
最初からフル機能を一気に導入すると、初期投資額が大きくなり、現場の混乱も生じやすくなります。
たとえば、「まずは勤怠管理から」「帳票ツールだけ使ってみる」といった段階的な導入を行うことで、初期費用を最小限に抑えつつ、日常業務のキャパシティも確保できます。
さらに、使っていくうちに必要な機能と不要な機能の分別がつくようになり、自社に最適なオプションのみに絞っていけるのもスモールスタートのメリットです。
このように、いきなり大規模なシステム導入に踏み切るのではなく、段階的に必要なツールから導入していくことが、コスト面・運用面の両方で負担を減らすカギとなります。
【注意点】建設DXは「コスト」ではなく「投資」!費用に見合う価値がある理由
「DXはお金がある企業がやること」「人が足りていないうちにはまだ早い」と感じている方もいることでしょう。
特に、日々の現場業務で忙しくされている職人や経営者の方にとっては、貴重な時間とお金をDXに割くのは惜しく思われるかもしれません。
しかし建設DXは単なるコストではなく、将来的な利益につながる「投資」と考えられています。
今一番時間を取られている業務を効率化できれば、より生産性の高い業務に人員と時間を割けるようになり、コスト削減はもちろん企業全体の売上アップにもつながります。

実際にあった事例として、埼玉県川口市にある中原建設株式会社では、現場にDXツールを取り入れたことで時間外労働が26.7%削減されたという結果も現れています。
まずは、今の仕事のやり方を見直すところから始めてみてください。
使い慣れていくうちに、作業時間の短縮や人件費の削減といった「数字としての効果」も、次第に見えてくるはずです。

その他にも、建設DXを進める中で直面しがちな課題もまとめていますので、こちらの記事もご覧ください。
▶参考:建設DXの課題とは?現場だけじゃない、業界全体が抱える本質的な問題を解説
建設DXの費用に関するよくある質問
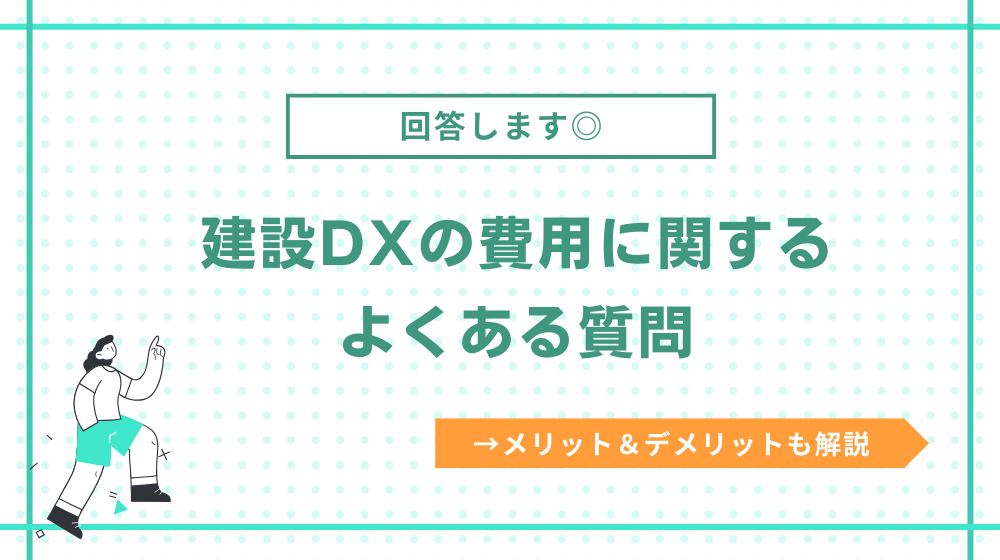
最後に、建設業で起業・経営をしている方から寄せられる質問の中でも特に多いものを取り上げ、一つひとつお答えしていきます。
Q.結局、建設DXを始めるにはまず何からやればいい?
まず取り組むべきは、「自社の課題を明確にすること」です。
たとえば「現場との連携が遅い」「工程が属人化している」「手書きの帳票が手間」など、日々の業務でストレスを感じている部分があれば、それがDX導入のヒントになります。

現場スタッフの愚痴や不満が、業務効率化の思わぬ糸口になることもあるかもしれませんよ。
今の課題が分かれば、そこから「勤怠管理をアプリ化する」「原価管理をクラウドに移行する」など、最も効果の高そうな分野に絞ってスモールスタートするのがおすすめです。
▶参考:建設業がまず行うべき業務効率化とは?効率化に成功した事例も紹介!
Q.月額制と買い切り型、どっちが得なの?
それぞれにメリットがありますが、結論から言えば「企業の規模・導入期間・保守の要不要」で総合的に判断するのがベストです。
| 比較項目 | 月額制 | 買い切り型 |
|---|---|---|
| メリット | ・初期費用を安くできる ・常に最新版が使える ・サポートが継続される | ・長期間使えばコストが割安 ・ネット環境が不要なケースもある |
| デメリット | ・累積コストが高くなることも ・契約期間中の解約に制限がある | ・初期投資が大きくなりやすい ・アップデートや保守が自己責任 |
| 向いている企業例 | ・少人数の事務所で必要機能だけ導入したい ・最新の機能やサポートを重視する | ・複数現場・長期プロジェクトを抱える企業 ・ネット接続が不安定な企業 |
たとえば、勤怠管理や写真共有アプリのように「常に最新機能を使いたい」といったニーズがある場合は月額制が向いています。
一方、機能が固定されており、長期で利用する前提なら買い切り型のほうが割安になるケースもあります。

あとはツールのデザインやサポート内容などを比較したり、複数のサービスから見積もりを取ったりして判断しましょう。
Q.建設DXでコスト削減になるって本当ですか?
はい、本当です。建設DXは「費用がかかるから負担」と思われがちですが、実は中長期的に見ると明確なコスト削減につながるケースが多くあります。
DXによって削減できるコスト
・紙の帳票を電子化 → 印刷・郵送コスト削減
・写真報告のクラウド化 → 移動時間・報告作業の短縮
・原価・工程の可視化 → 過剰発注や工程遅延の予防
・人手作業の自動化 → 残業時間の削減、ヒューマンエラーの防止
もちろん、導入直後から成果が出るわけではありません。
3か月、半年、1年と使い続け、自社の業務形態に合うようカスタマイズを続けることで、ようやく効果が現れ始めます。

実際、以下のように「DXを導入したことで時間も経費も節約できた」と感じている企業はたくさんあります。
一時的な支出ではなく、トータルで考えるよう意識しましょう。
▶こちらもチェック:【2025年】建設DXの事例を調査!参考になるポイントが沢山!
Q.DXってうちの規模(10人未満)でもやる意味ありますか?
十分に意味があります。むしろ、少人数で運営している会社ほど限られた人材で多くの業務をこなす必要があるため、情報共有のスピードや作業の正確性にこだわるべきでしょう。
また、大規模な企業の場合はアプリひとつ導入するのにも確認が必要ですが、小規模企業なら導入・運用の意思決定が早く、柔軟に仕組みを変えられるのも強みです。
Q.建設DXの効果っていつから実感できるの?
DXの効果を実感できるまでには、ある程度の時間がかかります。
導入するツールの種類や現場スタッフの年齢層にもよりますが、早くても3か月程度、実際に成果を感じられるまでには半年ほどかかるケースが一般的です。
特に原価・工程管理など複雑な仕組みを取り入れる場合は、予実管理の精度が向上するまでに3〜6か月程度の運用期間を要することも少なくありません。
導入後すぐに効果を求めるのではなく、「まずは使いこなせる状態をつくる」ことが最優先です。

定着を早めたい場合は、社内研修やベンダーによる導入サポートを活用し、使い方を丁寧に学べる場を設けましょう。
焦らず段階的に進めることで、結果として建設DXの費用に見合う確かな効果が見えてくるはずです。